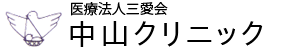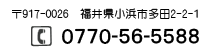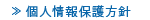脳神経外科
認知症について
◎認知症概論
※認知症とは
認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。認知症の診断に最も用いられる診断基準のひとつが、アメリカ精神医学会によるDSM-IVです。各種の認知症性疾患ごとにその定義は異なりますが、共通する診断基準には以下の4項目があります。
「DSM-Ⅳによる認知症の診断基準」①多彩な認知欠損。記憶障害以外に、失語、失行、失認、遂行機能障害のうちのひとつ以上。②認知欠損は、その各々が社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準から著しく低下している。③認知欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではない。④痴呆症状が、原因である一般身体疾患の直接的な結果であるという証拠が必要。
もっとも近年では、認知症診断の進歩により、こうした診断基準を満たす状態はかなり進行した認知症であり、早期治療にはつながらないという意見があります。そこで、早期診断を可能にする新たな診断基準も作成されています。
年をとるほど、認知症になりやすくなります。65歳以上70歳未満の有病率は1.5%、85歳では27%に達します。2020年には、日本における65歳以上の認知症患者さんは300万人を超すと推定されています。また、若くても脳血管障害や若年性アルツハイマー病のために認知症を発症することがあります。65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。認知症ほどではないけれど、正常な「もの忘れ」よりも記憶などの能力が低下している「軽度認知障害」が注目されています。軽度認知障害の方がすべて認知症になるわけではありませんが、この段階から治療を開始することで認知症の進行を遅らせるなどの効果が期待されています。認知症ではなさそうだと思っても、もの忘れの程度がほかの同年齢の人に比べてやや強いと感じたら、念のために専門医を受診することが早期発見・早期治療につながることになります。
※“認知症”と“高次脳機能障害”
認知機能とは、目や耳などを通して得られた様々な情報を正しく認識し、記憶、判断するという脳の高次機能のことであり、認知症とは広い意味では高次脳機能障害に相当します。その原因は様々で、主なものだけでも頭部外傷、脳卒中(脳血管障害)、内分泌代謝障害、炎症、腫瘍、てんかん、水頭症などがあげられます。しかし、一般に言う“認知症”とは、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など、年齢とともに徐々に進行する脳の変性疾患(変性型認知症)を意味していることが多く、頭部外傷や脳卒中などが原因の場合には高次脳機能障害と呼ばれることが多いようです。また、変性型認知症とまちがわれやすい疾患に、高齢者のてんかん、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍など、手術治療の対象となりうるものがあります。
◎認知症の症状
※認知症の症状
認知症の中核は“もの忘れ”ですが、なかでも経験記憶の障害が特徴的です。「さっきのことが思い出せない」ことが目立ちます。たとえば「夫婦で会話中に電話が鳴ったので、奥さんがそれに対応して数分後に再び席についた。そこで先刻の話題に戻ろうとしても、ご主人はその内容を思い出せなかった」というような例が典型です。また、すでに冷蔵庫にたくさん入っている食品を繰り返して買うような記憶障害の現れ方も少なくありません。健康なときには自分が経験したことは自然に覚えているものですが、認知症になるとこの経験記憶が障害されます。自分で言ったこと、したことを忘れるので、“そんなことは言っていない”、“そんなことはしていない”と本気で訴えるようになります。ご本人は自分が忘れていることに気づかず、ご家族や周囲の人々からおかしいと気づかれることになりますが、認知症のごく初期には周囲が気づく前に自分で“もの忘れ”に気づいている時期があります。この時期にはご本人がもの忘れを訴えることもあれば、不安で落ち込んだ状態になっていることもあります。病気の前段階かどうかを見極めるためには、はやめに専門家に相談することが必要になります。
※“もの忘れ”だけではない認知症の症状
認知症であっても記憶の障害以外の症状が先行する場合もあります。趣味にしていたことをしなくなった、根気がなくなった、何事にも関心がなくなった、喜怒哀楽を示すことがなくなってきた、ささいなことで激怒する、いつも同じパターンで行動しようとする、家族の気持ちが理解できない、異常な言動や行動がある、段差でつまずく、言葉が出てこない、いないはずの家族や知人が見えるなどで、これらは前頭葉と呼ばれる部位の症状と考えられています。もの忘れはそれほど目立たないことがあり、「認知症」=「もの忘れ」ではなく、障害されている脳の部位によって症状は異なります。
運動機能の障害はないのに意味のある動作、たとえば 「くわえたタバコにライターの火をつけること」 ができない(失行)、感覚機能の障害はないのに対象を正しく認知・認識できない(失認)といった障害もみられることがあります。よくあるのは方向感覚の悪さで、何度も行ったことのある娘の自宅を訪ねようとして道に迷うような例です。計画をしてその準備をし、首尾よくこなしてゆく能力、いわゆる「段取り能力」のことを実行機能といいます。そのような機能の障害の典型例として、女性なら料理のレパートリーが減り限られたメニューを繰り返しつくる傾向がみられます。
多くのご家族は、記憶など認知機能の障害ではなく、精神症状や行動異常をきっかけに受診されます。暴言・暴力、徘徊・行方不明、幻覚・妄想などが問題になりやすく、数カ月から数年にわたって持続し在宅での介護ができなくなる原因になりがちです。
◎認知症の治療
※認知症の治療はできるだけ早期に
認知症は脳の神経細胞が変性する疾患であり、治すには神経細胞を再生させるだけでなく新しい神経細胞の連絡網をつくる必要があります。残念ながら現在の医療では神経の連絡網をもとどおりに再生させることはできず、一度認知症になると回復は困難です。したがって、神経細胞の変性があまり進行していない段階から、できるだけ軽い症状のまま過ごせるよう進行を遅らせることが治療の目的となります。
現時点での認知症の治療薬は、基本的にアルツハイマー型認知症に対するもので塩酸ドネペジルなど抗コリンエステラーゼ阻害薬が有効とされています。また、適応は今のところありませんが、レビー小体型認知症に有効なことがあります。しかし、塩酸ドネペジルも神経を再生させる薬ではなく、多少進行を抑えるにすぎません。なお、治せる認知症として代表的なものである正常圧水頭症については手術の有効性が示されています。
認知症を根治できる薬物療法が存在しない現状では、効果的な非薬物療法により薬物療法を補って治療効果を高める必要があります。認知症への心理・社会的な治療アプローチ(非薬物療法)の標的は、認知、刺激、行動、感情、の4つに分類されます。有名な回想法は、認知症患者さんでも比較的保たれている長期記憶を生かせることや、一人ひとりの経験や思いを尊重できることから注目されています。 認知症の精神症状・行動異常の中には、対応の仕方で改善できるものもあれば、どうしても薬物に頼らざるをえないものもあります。忘れてならないのは、デイケアなど各種の非薬物治療も不可欠だということです。これに関しては、日々の介護で心身ともに疲れきっている介護者への介護という視点も大切です。そのためには、介護保険など社会的支援制度の概要を知る必要があります。
【アルツハイマー型認知症】
アルツハイマー型認知症は、脳のアミロイドβの蓄積と神経原線維変化の両方が重なって引き起こされると考えられていますが、本当のところはまだ解明されていません。最近の研究によると神経原線維変化は以前に考えられていたよりも早期から出現している可能性があり、アミロイドβと神経原線維変化がどのようにかかわるのか研究されている段階です。 典型的なアルツハイマー型認知症の脳では、嗅内野や海馬などの側頭葉内側から神経細胞の変性が始まり、側頭葉外側、後部帯状回、頭頂葉と広がり、前頭葉の障害は後の方になります。人によっては側頭葉内側よりも頭頂葉などの大脳皮質の変性が強い場合もあることが知られています。これらの領域は、後頭葉を含めて外界からの情報を処理する領域になります。アルツハイマー型認知症の典型的な症状は経験記憶の障害です。財布や書類など大切なものであってもどこに置いたか思い出せず、しばらく前に言われたことや自分でしたことを忘れてしまうため何度も同じことを聞いたり言ったりします。患者さんと何気ない話をしているときは全く正常な会話に思えるのに、実はとりつくろっていて虚偽の話であったりします。薬の管理ができなくなって家族に気づかれることもあります。また、外来診療でしばしばみられる所見に“振り向き”があります。何かを質問されても覚えていないので、家族の方を振り向いて代わりに答えてもらおうとします。さらに症状が進行すると側頭葉外側や頭頂葉の障害があらわれます。特に頭頂葉の症状で目立つのは、場所がわからない、着衣ができない、時計を見ても時間がわからないなどの症状です。顔貌の認識も障害されるので、顔を見ても誰だかわからなくなります。さらに進行して前頭葉が障害されると複雑な物事の遂行ができなくなり、やがてトイレの始末などができなくなります。
【レビー小体型認知症】
1912年にDr. Lewyがパーキンソン病の患者さんの脳で神経細胞内に高頻度に出現する小体を報告したのが始まりで、彼の名前を冠してLewy body (レビー小体)と呼ばれるようになりました。この小体が出現している神経細胞は元気がなくなっていますが、その原因はまだ明らかではありません。その後、レビー小体が認知症の患者さんでも認められることがわかり、現在ではレビー小体型認知症はパーキンソン病と合わせてレビー小体病として扱われるようになってきています。レビー小体病は、脳幹型(45%)、辺縁型(移行型)(25%)、新皮質型(30%)に分けられ、脳幹型がいわゆるパーキンソン病に相当します。レビー小体病の患者さんの脳にはアルツハイマー型認知症の特徴を示す病理所見がしばしば混在しています。特に新皮質型ではアルツハイマー型認知症の所見が高頻度に認められ、臨床的にも症状はアルツハイマー型認知症に似ています。 レビー小体型認知症の患者さんは、アルツハイマー型認知症の患者さんと比べて海馬の萎縮が軽微であることが多く、心理検査でもアルツハイマー型認知症とは異なるパターンを示すことがしばしばあります。レビー小体型認知症の特徴は、パーキンソン病を伴う、平均発症年齢は60歳、大脳皮質や海馬の萎縮は軽度、注意や明晰性の変動が中核、幻視・記銘力低下より記憶の再生障害が目立つ(海馬ではなく前頭葉由来の記憶障害)、認知機能障害に顕著な変動がある、初期にはうつ病と診断されることが多い(うつ病の頻度が高い)などです。レビー小体型認知症の幻視・妄想の典型は、人物・小動物・虫が多く、「ベッドの脇に孫が座っていた」、「虫(蛇)が壁を這っていた」、「カーテンが洋服や人に見えた」、「(既に死亡している)親戚が部屋にいた」などです。
【前頭側頭型認知症】
アルツハイマー型認知症が知覚系大脳皮質の病変を主体とするのに対し、運動系大脳皮質病変を主体とする非アルツハイマー型の変性性認知症疾患を包括的に捉えた疾患群の病名です。前頭側頭型認知症の症状の特徴は前頭葉の機能障害を主体としたもので、病初期にあってもご本人にはまったく病識がありません。ほとんどが65歳以下とアルツハイマー型認知症よりも若い年齢で発症し記憶の障害は目立ちません。自発性が低下してじっとしているかと思うと常同的な行動を示すことがあります。抑うつ感や悲哀、不安感は目立ちません。寝てばかりいるので声をかけても、「何か食べる?」「知らん」、「散歩する?」「知らん」と何も考えずに即答することがしばしばあります。同じ言葉を意味もなく繰り返す、同じところを同じ時間に周遊する、など日常行動のパターンにバリエーションがなくなってきます。ささいな事にこだわる傾向があります。同じものを異常なほど繰り返して食べたり、食欲が不自然に旺盛になることもあります。料理のメニューを考えて、買い物をして、作る順番を考えて段取りよく調理するといった複合的な行動が完遂できなくなります。ある行為を続けて行うことができず、根気がないようにも見えます。周りのことを気にせず自分勝手に行動しがちです。周囲の人の気持ちは意に介さず、共感することもありません。注意されると激しく怒ります。ルールは無視して、万引きなどの反社会的な行動をしても反省するそぶりは示しません。このような症状は家族に精神的にも大きな負担がかかるため、地域社会でのケアが必要になります。
【脳血管性認知症】
脳血管性認知症は、アルツハイマー型認知症に次いで多いとされている認知症です。脳梗塞や脳出血、くも膜下出血など、脳の血管が詰まったり出血したりして神経細胞が機能を失うことによって認知症が起こります。血管の病気を引き起こす危険因子として、高血圧、糖尿病、心疾患、脂質異常症、喫煙などがあります。脳血管性認知症は、生活習慣病によって引き起こされることが多いといえます。 脳梗塞や脳出血などの脳血管障害をきっかけに認知症状が急激に出現したり、よくなったり悪くなったりを繰り返しながら進行したりします。症状は、障害された脳の部位によって異なります。アルツハイマー型認知症と診断された方であっても血管障害を合併していると、脳血管性認知症の症状をきたす場合があります。初期段階では、自分の認知機能低下を認識していることもあります。「これくらいできないの?」、「どうしてわからないの?」などという言葉を投げかけられても、ご本人はどうすることもできません。認知症でできないことが増えていくことを自覚するのは、ご本人にとっては大変辛い状況です。そのことに配慮し、辛い状況を受け止める言動を心がけましょう。